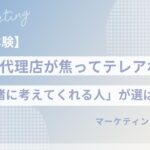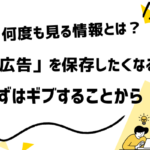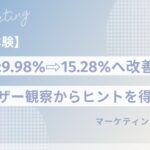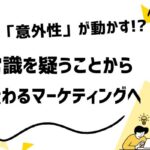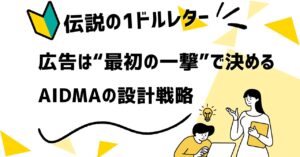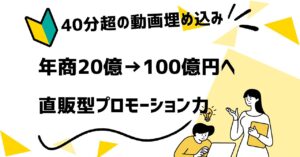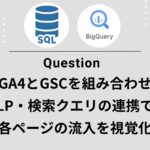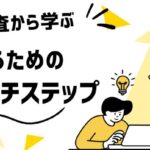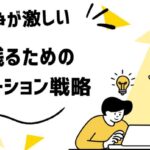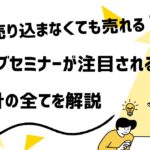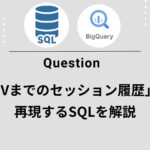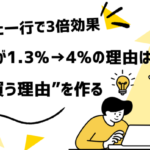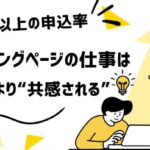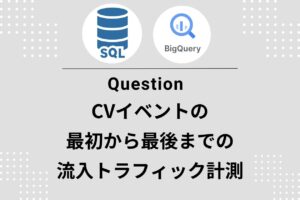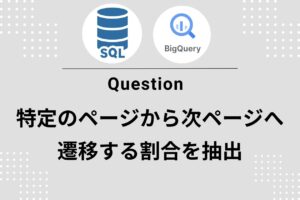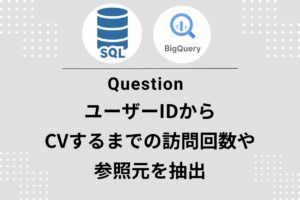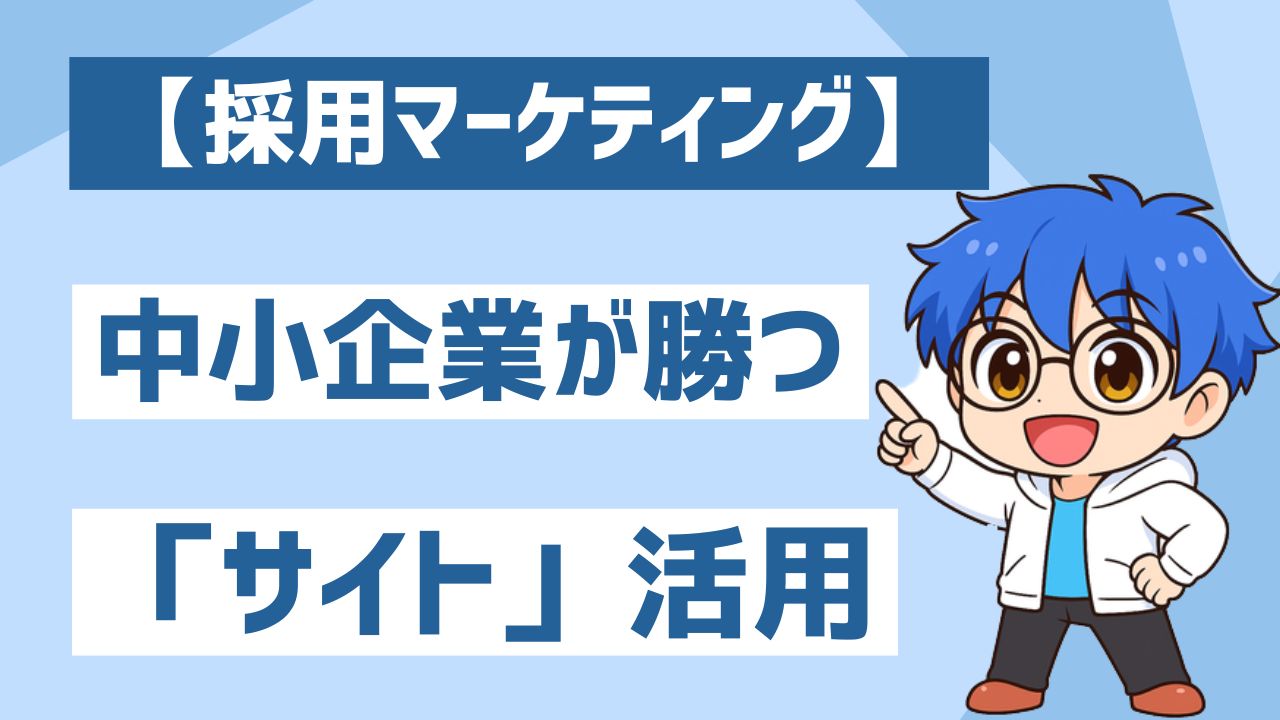
「採用サイトって本当に必要なの?」
正直に言うと、最初は疑っていました。

求人媒体に出しておけば、とりあえず応募は来る。
わざわざ採用サイトをつくるなんて、コストと手間ばかりかかるだけじゃないの?
そう思っていましたが、実際にデータを見たり、現場で話を聞いたりすると気づきました。
👉ナビサイトでは伝えきれないことが山ほどある。
ある会社の採用担当の方はこう話していました。
「ナビサイトには“明るい職場です”としか書けなかった。
でも本当は“子育てしながら安心して働ける仕組み”を伝えたかったんです」
この一言を知って、ハッとしました。
求職者が知りたいことと、会社が伝えたいことがズレているんですよね。
だから、入社しても「思っていたのと違った…」となり、早期離職につながってしまう。
このとき僕が強く思ったのは、
「採用サイトは単なる飾りじゃなく、会社の武器になる」
ということです。
Contents
採用サイトをつくる意味
1.情報を自由に出せる
ナビサイトのフォーマットでは語りきれないこと、ありませんか?
「実際のキャリア事例」「社員インタビュー」「仕事のやりがい」…
自社サイトなら全部出せます。
僕自身もGA4や広告の数字を分析するなかで感じるんですが、
ユーザーは“自由な情報発信”に一番反応するんです。
企業の色や温度感を、ナビサイトでは拾いきれない。
2.ミスマッチを防げる
採用って「入ったけどすぐ辞めた」が一番つらいですよね。
これは企業にとっても本人にとっても不幸です。
僕も色々な離職理由のヒアリングを見てきましたが、
「社風が合わなかった」「思った仕事と違った」
これがめちゃくちゃ多いんです。
だからこそ、最初から「リアルな情報」を出すことが大事。
「この会社は合う」「自分には合わない」
求職者に判断してもらえれば、ミスマッチを防げるんです。
3.新しい集客経路になる
Googleしごと検索や求人検索エンジンと連動できるのも強い。
ナビサイト依存から脱却できるんですよね。
僕も広告を回していて痛感しますが、
「母集団を増やす競争」では中小企業は大手に勝てない。
でも、自社サイトなら「指名検索」「地域+職種」でピンポイントに拾える。
これが大きな武器になるんです。
よくある採用サイトの失敗

ここからは「ありがちなNG例」を一気に整理します。
僕自身もクライアントさんと議論するときに、よく出てくる話です。
❌イメージ動画だけ
「カッコよさ」に力を入れすぎると、現実の姿とのギャップが大きくなります。
求職者は華やかさよりも日常の雰囲気や実際の働き方を知りたいのです。
社員の座談会や現場の様子をそのまま見せるほうが、誠実さが伝わり安心感につながります。
❌決まりきったメッセージ
「売上過去最高!」は会社の強みを示すには良いですが、求職者が知りたいのは自分の成長ストーリーです。
企業の数字だけでは未来像が描けません。
むしろ「ここで得られるスキルやキャリアの可能性」を提示することで、応募意欲が高まります。
❌意味不明キャッチコピー
抽象的な言葉遊びは一瞬の印象には残りますが、行動にはつながりません。
読み手が「結局どんな会社?」と混乱してしまいます。
具体的な仕事内容や価値提供をシンプルに表現することで、共感と行動のきっかけになります。
❌ありきたりな魅力
「アットホーム」「顧客第一」といった表現は、他社との差別化になりません。
ありきたりな言葉は求職者の心を動かさないのです。
代わりに、社員の体験談や実際のエピソードを伝えることで、共感を生み具体的なイメージがわきます。
❌主観的な社風・社史
経営者や人事が語る「明るい職場です」は、求職者にとって信用しづらい表現になりがちです。
実際の社員の声と食い違うこともあります。
現場社員のコメントやデータに基づく情報を出すことで、信頼性と納得感を高められます。
❌数字だけ並べる
「平均勤続年数6年」とだけ書かれても、読み手は短いのか長いのか判断できません。
数字は解釈が必要だからです。
「教育が充実していて独立者が多い」など背景を説明することで、その数字がポジティブに映ります。
❌求める人材像を一般論で書く
「責任感ある人」「主体的に動ける人」はどの会社も言っています。
書けば書くほど独自性がなくなります。
むしろ「こんな人は合わない」という基準を出すことで、ミスマッチを減らし、お互いにとって健全な採用が可能になります。
❌オシャレすぎるデザイン
見栄えにこだわりすぎると、肝心の応募導線が見えにくくなります。
サイトは芸術作品ではなく行動を促すためのツールです。
「応募」「資料請求」などのCTAを分かりやすく配置することが成果につながります。
❌情報詰め込みすぎ
欲張ってすべてを載せると、読み手は途中で離脱します。
情報過多は集中力を奪う原因になります。
必要な情報を整理し、ストーリーとして順序立てて見せることで、理解しやすくなり応募行動にもつながります。
❌誰向けか不明
「誰でも歓迎」スタンスでは結局誰にも響きません。
曖昧な発信は時間とコストの無駄になります。
具体的なペルソナを設定し、その人物像に合わせた言葉や構成にすることで、刺さる情報発信が可能です。
中小企業の採用は「合う人に届けばOK」

ここで一番伝えたいのはこれ。
「母数を増やしてふるい落とす」時代は中小企業には合わない。
大企業は知名度で集めて選別できます。
でも中小企業は、数を集めるより「合う人にだけ届く」ことが重要。
たとえば「地元で腰を据えて働きたい20代」や「子育てと両立しながら専門性を活かしたい人」など、具体的な像を思い浮かべることが大切です。
そうすることで、メッセージやサイトの構成が自然と尖り、必要な人にだけ届くようになります。
そして、その1人が応募してくれれば採用は成功。
母数よりも質を重視する姿勢が、結果的に定着や活躍につながるのです。
だから「採用サイトは合う人に届ける武器」なんですよね。
勝てる採用サイトはLP型
じゃあ実際どう作ればいいの?
答えはシンプルで、
👉ランディングページ(LP)型の採用サイトにすること。
- 縦長構成
- ストーリーで流れを作る
- 行動導線(応募・資料請求)を必ず入れる
これはマーケティングの考え方そのものです。
SNSや広告から流入した人を、そのまま応募につなげる。
中小企業が最短で成果を出すなら、この設計が必須です。
まとめ

最後に、僕がこの記事を通じて感じたことをもう一度。
- 採用サイトは「カッコよさ」で勝負する場じゃない
- 会社のリアルと未来を伝え、合う人に刺さる武器である
- 中小企業は「母数勝負」を捨て、「共感勝負」に切り替えるべき
色んな案件を見てきて思うことは、結局、採用はマーケティングそのものなんです。
ターゲットを決めて、刺さるメッセージをつくり、行動を促す。
採用サイトは、その一番の武器になります。
大手の真似ではなく、あなたの会社にしかない「リアル」を出してみてください。
きっと、共感して応募してくれる人に届くはずです。