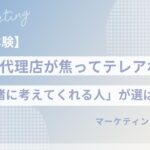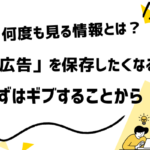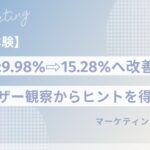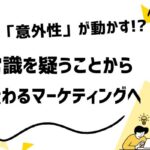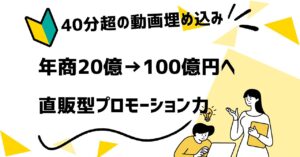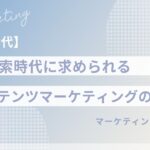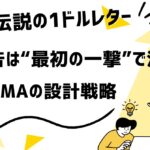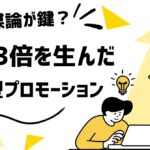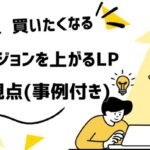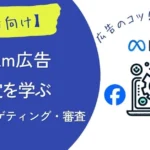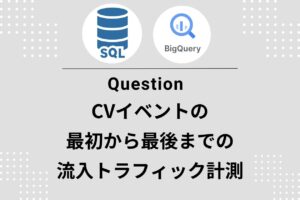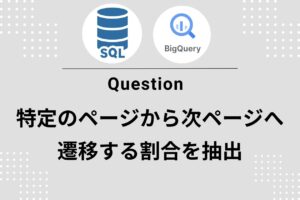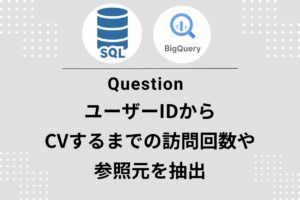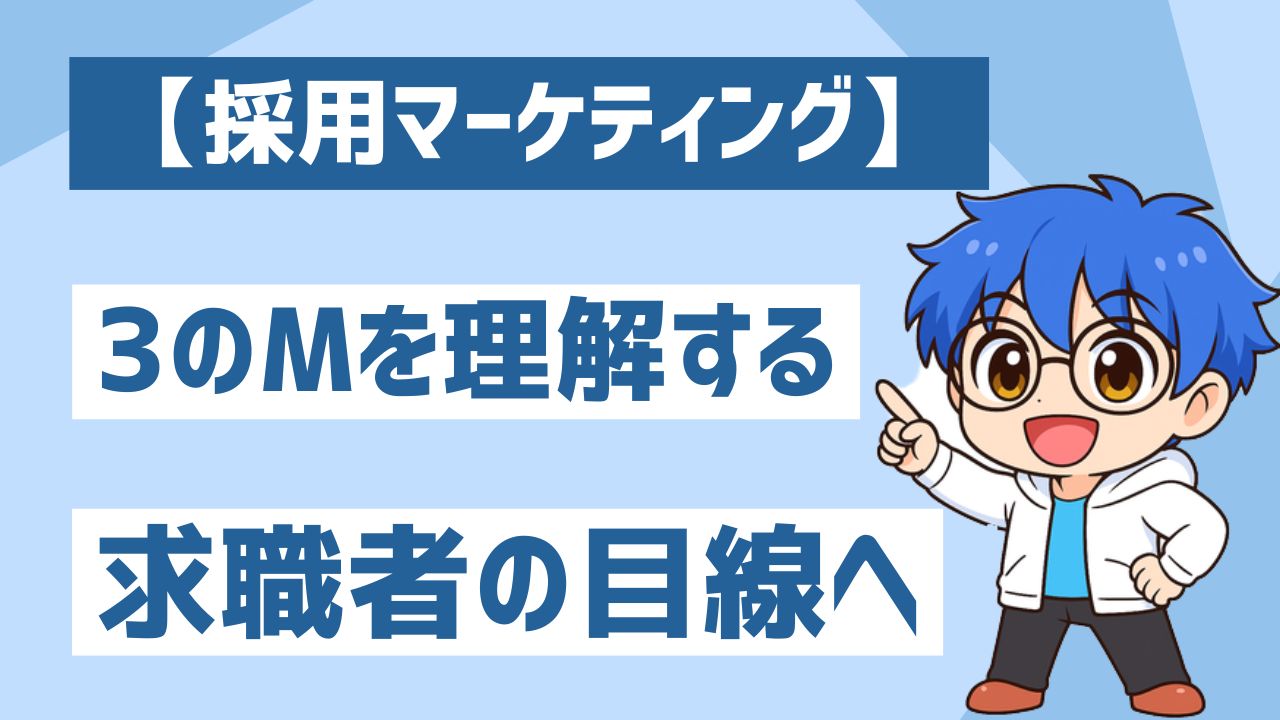
採用もうまくいくときは「たまたま」ではありません。
ダイレクトマーケティングの基本である
・Market(誰に)
・Message(何を)
・Media(どの手段で)
3つが噛み合ったときにだけ成果が出るんです。
広告や採用の現場で「応募が来ない…」という相談をよく受けますが、掘り下げてみるとだいたいこの三要素のどこかがズレている。
だからこそ、採用で悩んでいる企業は三つのMをセットで見直す必要があるんです。
Contents
Market(誰に届けるか)

多くの中小企業は、ここを一番誤解しています。
商品やサービスなら顧客を分析するのに、採用になると「うちは魅力的だから来てくれるはず」と一方的な発信に終始しがちなんです。
ナビサイトに載せれば応募が集まる時代は終わりました。
今は求職者が細分化され、「誰に」「何を」「どう届けるか」を明確にしなければ行動は起きません。
つまり企業は「選ぶ側」ではなく、「選ばれる存在」にならなければならないんです。
企業側が「自分たちの発信が独りよがりになっていないか?」を一歩引いて見直すことが大切です。
「相手の立場でどう見えているか?」を意識するだけで、発信内容はまったく変わります。
ある採用担当者は「自分の会社の魅力を伝えているつもりだったのに、学生からは“どこも同じに見えました”と言われた」と振り返っていました。
伝えたいことと、受け取られることの差は想像以上に大きいんです。
ペルソナを明確にする
じゃあどうやって「Market」を具体化するのか?
答えはペルソナ設定です。
「誰に来てほしいのか」を、まるで実在する人物かのように描きます。たとえば、
- 「10年以内に独立を視野に入れて幅広い経験を積みたい学生」
- 「大企業の歯車になるのを不安に思い、自立を目指す若手」
僕が見てきた事例では、このようにペルソナを細かく定義した企業ほど、狙った人材からの応募が集まりやすい。
曖昧なターゲット設定では、結局誰にも響かないんです。
作ったペルソナを「本当に自社が受け入れられる人物像か?」と問い直すこと。
欲しい人物像と、実際にフィットする人物像の間にズレがないかチェックすることが成果につながります。
中小企業が打ち出せるメリット

「うちは大企業みたいに給与や福利厚生で勝てないから…」と諦める声もよく聞きます。
でも、それ以外にも強みは必ずあるんです。
実際に社員にインタビューすると、
- 「釣りに行きやすい」
- 「クラブ活動が楽しい」
- 「月1回、経営陣に意見を言える」
- 「妻の実家に近い」
こんな“本音”が出てきます。
これこそ、求職者にとってのリアルなベネフィット。
制度や数字ではなく、働く人の言葉の中にこそ魅力が隠れているんです。
自社の「強み」と思っていることが、本当に求職者にとってメリットかどうかを問い直す。
“企業の言いたいこと”と“候補者が知りたいこと”のギャップを自覚できれば、発信の解像度が一気に上がります。
「強み」より「ベネフィット」を伝える

マーケティングでよく出てくるUSP(UniqueSellingProposition)は「顧客にとっての独自のベネフィット提案」。
採用でもまったく同じです。
「社会のために役立つ」なんて抽象的な言葉より、
- 「入社3年でプロジェクトを任される」
- 「幅広い領域に挑戦できる」
こうした成長や自己実現のベネフィットを提示するほうが、求職者には刺さります。
メッセージを読んだ求職者が「自分の未来」としてイメージできるかを考えること。
伝える側の“満足”ではなく、受け取る側の“解釈”を常に意識しましょう。
私の会社では、「御社の説明会で“3年でリーダーを任される”と言われて驚いた」と話していました。
その瞬間に目が輝いたのを見て、数字よりも具体的な未来像こそが人を動かすと実感しました。
売り込み型採用の限界
今回紹介するのが船橋屋の成功事例です。
老舗和菓子メーカーがナビサイト上で若手社員によるブログ発信を始め、最初は250人の応募が、数年で1万6000人以上に増えた。
ポイントは「会社の魅力を押し売りしなかった」こと。
若手社員の日常や入社理由、休日の過ごし方を正直に書いただけ。
それが求職者の共感を呼び、「ここなら自分も働けそう」と思わせたんです。
採用活動も広告と同じで、売り込みすぎると引かれるんですよね。
自社の発信が「宣伝っぽく見えないか」を客観視すること。
候補者が「自然だ」と感じるかどうかを常に点検することで、共感が生まれます。
実際に船橋屋のブログを読んだ学生は「他社は作り込んでいて引いたけど、ここは自然体で安心した」と話しています。
人の心は“本音の温度”に敏感なんです。
求職者が本当に見ているもの

電通の調査(2019年)でも明らかですが、就活生が魅力を感じるのは「給与」や「福利厚生」よりも、
- 社員がいきいき働いていること
- ワークライフバランスがあること
- 自分に合った職場の雰囲気
つまり、求職者が知りたいのは「ここでやっていけるかどうか」。
- 先輩はどんな人か?
- 社長はどんな人か?
- 若手にどんなチャンスがあるのか?
これらを具体的に発信するだけで、応募の質は大きく変わります。
情報を出すとき「自分たちにとって当たり前すぎて説明を省いていないか?」をチェックすることが大事です。
社内の日常は、外の人には十分に新鮮で貴重な情報になります。
社内アンケートを取りましたが、「給与よりも“どんな先輩がいるか””リモートが可能か”のほうが気になる」とはっきり言っていました。
当たり前すぎて見落とす情報こそ、候補者にとって一番大切な材料になるんです。
「転職ありき」で就職を考える時代
いまの若手は企業への依存ではなく、「スキル」「経験」「市場価値」を軸に就職を考えています。
だからこそファーストキャリアに求めるのは「成長できる環境」。
中小企業はここが強みです。
一人ひとりの役割が広いから、自然と業務全体に関わりスキルの幅が広がる。
この経験は転職後も生きる「市場価値」になるんです。
実際、ダイレクト出版は「社会の歯車にならない」「自立できる力が身につく」と訴求し、優秀な学生を集めていました。
候補者のキャリア視点で「自社で得られる経験は市場でどう評価されるか?」を考える。
自己満足の発信にならないよう、外部の評価軸で自社を点検しましょう。
僕の場合は面接現場で「私のやりたいことと御社が求める人材にマッチしますか」と直球で聞いたことがあります。
そこで具体的に答えられるかどうかで、信頼度が一気に変わるんです。
コロナ禍で問われた「Market」への想像力
コロナ禍で内定取り消しが相次いだとき、ノジマや松屋フーズが「取り消された学生を採用します」と打ち出しました。
この姿勢に多くの学生が救われ、「この会社なら信頼できる」と感じたんです。
結局、Market=求職者をどれだけ想像できるかが成果を分ける。
数字や条件だけではなく、「相手の不安にどう寄り添えるか」で企業へのロイヤリティが生まれます。
採用広報の発信を「もし自分が学生や転職者だったら」と読み直してみましょう。
その視点があるかないかで、文章のトーンや伝わり方が大きく変わります。
まとめ:三つのMを採用に当てはめると?
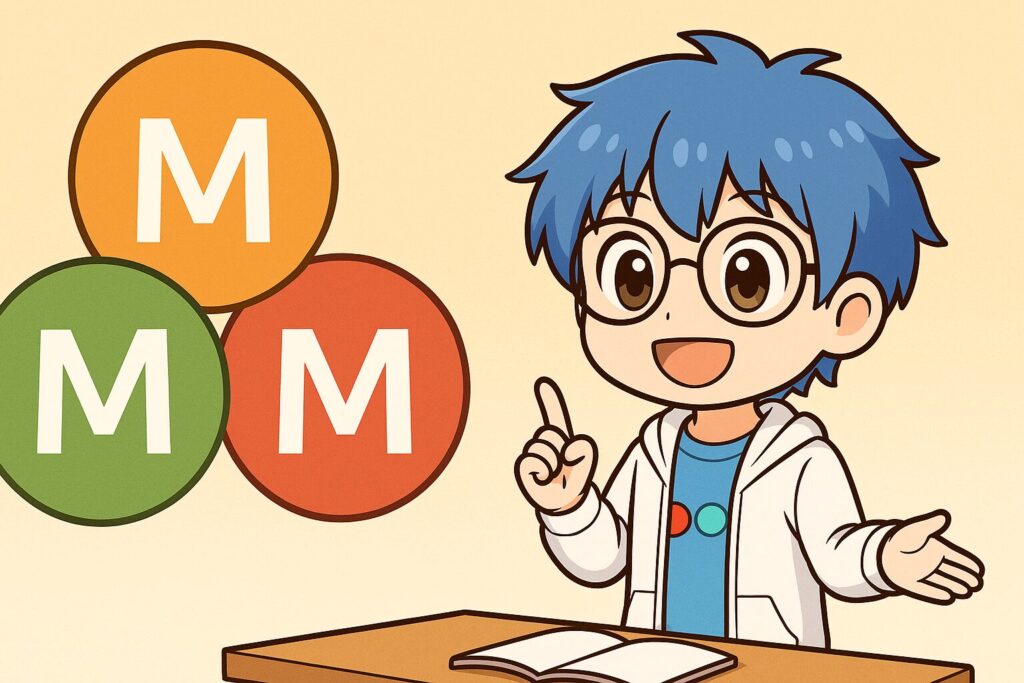
- Market:求職者を正しく理解し、ペルソナを描く
- Message:成長ややりがいといったベネフィットを伝える
- Media:売り込みではなく、自然に伝わる手段を使う
採用で行き詰まっているときは、この三要素のどこが欠けているかを見直してみてください。
僕も現場で何度も経験しましたが、三つが揃った瞬間に「応募が集まる仕組み」が動き出します。
発信のたびに「自分たちが伝えたいこと」ではなく「相手が受け取りたいこと」になっているかを問い直すが大事です。
その習慣こそが、三つのMを正しく回す最大のポイントです。
採用もマーケティングも、最後は“人の心”。
数字や理論だけではなく「どんな気持ちで読まれているか」を想像できる企業が、本当に選ばれる企業になるんだと思います。